『ジュリアン』Jusqu'a la garde【感想・レビュー】
第74回 ヴェネチア国際映画祭 最優秀監督賞受賞
スタッフ
監督:グザビエ・ルグランキャスト
レア・ドリュッケール:ミリアム・ベッソンドゥニ・メノーシェ:アントワーヌ・ベッソン
トーマス・ジオリア:ジュリアン・ベッソン
マティルド・オネブ:ジョゼフィーヌ・ベッソン
あらすじ
両親が離婚したため、母ミリアム、姉と暮らすことになった11歳の少年ジュリアン。離婚調整の取り決めで親権は共同となり、彼は隔週の週末ごとに別れた父アントワーヌと過ごさねばならなくなった。母ミリアムはかたくなに父アントワーヌに会おうとせず、電話番号さえも教えない。アントワーヌは共同親権を盾にジュリアンを通じて母の連絡先を突き止めようとする。ジュリアンは母を守るために必死で父に嘘をつき続けるが、それゆえに父アントワーヌの不満は徐々に溜まっていくのであった。家族の関係に緊張が走る中、想像を超える衝撃の展開が待っていた。(公式HPより)
音が想像させるもの
この作品は、暴力を振るう父親との関係を切り離すことができず、その迫りくる恐怖に怯える子供の視点から、描かれているが、特に「音」を使った演出が素晴らしく、恐ろしい。劇中、敢えて「そのもの」を直接描くのではなく、カメラのフレームを固定し、音により、観客の想像を掻き立てるシーンが効果的に使われている。姉の学校でのシーンも、その事柄に意味があるようにみえるが、それは、このあと起きる展開が映像という形だけではなく、音というもので表現されますよ、という観客へのメッセージになっている。エンドロールまで気を抜かないで
最近、特にエンドロールまで丁寧に制作されている作品も増えてきているが、この作品もそのひとつ。文字だけが流れるものだと先入観で気を抜いていると、この作品の楽しみをひとつを楽しみそこねてしまいます。エンドロールは、決して、タイアップ曲を流す場所ではなく、映画の一部である。それを体感できる演出がされていて、映画を観たあとの余韻を後押しする効果が素晴らしい。描かれていないことをイメージして
この物語の鍵として「嘘」がある。冒頭のシーンでは、どちらも「真実」を話しているかのようにみえるが、物語が進んでいくにつれ、「真実」が明らかになっている。この家族、主人公のジュリアンには、この冒頭を迎えるにあたる過去があり、彼の表情がそれを物語っている。私たちは、彼のその表情から、どうして彼がそんなに怯えるのか、を想像する必要があり、また、想像することによって、恐怖が増していく。映画や小説は、そのすべてを描けばよいというものではなく、観客や読者がいて、はじめて完結する。この作品では、そんなことを体感することもでき、体感できることが恐ろしい。作品全体として
監督の長編デビュー作とは思えない演出とジュリアンを演じるトーマス・ジオリア君の演技が印象に残る作品。ストーリーや企画が斬新といったものではないが、その映像からは、観客へ説得力のある「恐怖」を与え、記憶に残る作品に仕上がっている。スプラッシュホラーなど直接的な表現ばかりが、人の心に恐怖を生み出すわけではない。頭の中で恐怖のイメージが広がっていく。そんな作品。おススメ『ジュリアン』公式サイト
https://julien-movie.com/







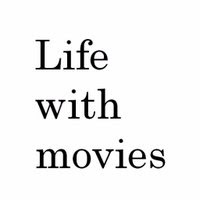
0 件のコメント:
コメントを投稿