(C)2018 NORD-OUEST FILMS-ARTE FRANCE CINEMA
第31回 東京国際映画祭 東京グランプリ、最優秀脚本賞
スタッフ staff
監督・脚本:ミカエル・アース Mikhael Hers脚本:Maud Ameline
出演 Cast
ヴァンサン・ラコスト Vincent Lacoste:ダヴィッド David Sorelイゾール・ミュルトリエ Isaure Multrier:アマンダ Amanda Sorel
ステイシー・マーティン Stacy Martin:レナ Lena
オフェリア・コルブ Ophelia Kolb:サンドリーヌ Sandrine Sorel
あらすじ
夏の日差し溢れるパリ。便利屋業として働く青年ダヴィッドは、パリにやってきた美しい女性レナと出会い、恋に落ちる。穏やかで幸せな生活を送っていたが 突然の悲劇で大切な姉が亡くなり、ダヴィッドは悲しみに暮れる。そして彼は、身寄りがなくひとりぼっちになってしまった姪アマンダの世話を引き受けることになる…。親代わりのように接しようとするが、まだ若いダヴィッドには荷が重く、戸惑いを隠せない。アマンダも、母親を失ったことをなかなか受け入れられずにいる。互いに不器用で、その姿は見ていてもどかしく、しかし愛おしい。悲しみは消えないが、それでも必死に逞しく生きようとするアマンダと共に過ごすことで、ダヴィッドは次第に自分を取り戻していく(公式HPより)
2019年6月21日(金曜)上映後Q&Aより(ネタバレ含みます)
ミカエル・アース監督(以下、監督)ヴァンサン・ラコスト
聞き手:矢田部吉彦 東京国際映画祭プログラミング・ディレクター
Q(矢田部):この作品を製作するきっかけは。
A(監督):映画を1本製作するにあたっては、いくつもの要素が集まって、創るに至ります。また、この作品では、パリの「今」も描きたいと考えていました。そして、ヒロインだけでなく、子供とともに成長していく「父性」も描きたいと考えていました。前作までの私の作品とは異なり、感情をストレートに描いています。
Q(矢田部):この作品とどのような形で出会いましたか。
A(ヴァンサン・ラコスト):ミカエル・アース監督の前作『サマーフィーリング』も拝見していて、お気に入りで、一緒にお仕事ができれば、と考えていました。事前に脚本を読ませていただき、現代のパリの描き方や作品に光が差し込んでいるところが印象的でした。この作品は、残された家族の再生を描いた物語ですが、テーマの扱い方が興味深かった。これまで出演してきた作品は、コメディが多く、この作品(シリアスなドラマ)に出演することに対する「怖さ」もありましたが、興奮する体験でもありました。
以下、観客からの質問
Q:ヴァンサン・ラコストさんをキャスティングした理由は、なんでしょうか。
A(監督):彼の中には、気品や軽さ、そして自然に持っている「光」のようなものがあると感じています。この作品は、テーマが重いので、彼が適役だと思いました。また、彼から溢れてくるものが素晴らしいということも知っていました。ただ、子役を探すのは、難しかったです。
Q:この役を演じるにあたり、テロ関連作品を観たり、本を読んだりといった準備をされましたか。
A(ヴァンサン・ラコスト):特に、この作品のために観た作品や読んだ本があるわけではありません。テロの被害者が書いた作品やインタビューも特に読んでいるわけではありません。なぜなら、主人公のダヴィッドに起きたことは、誰にでも起こりうることだからです。もちろん、脚本を暗記し、また、撮影は脚本と同じ時間順にされるわけでもありませんので、シーンの並びは記憶してむかいます。父性の醸成など難しい部分がありましたが、監督が良い雰囲気を作ってくれました。そういう撮影環境を作ることは大切なことだと思いますし、また、その環境に身を任せていきました。結果、感情を無理に作ることなく、泣くこともできました。
Q:再生の物語であると同時に、主人公ダヴィッドにとっては、レナとの関係性などからは、人生を取り戻す物語を感じましたが、そのように描いたのでしょうか。また、アマンダの演技は素晴らしかったですが、素人からスカウトしたイゾールさんへの演技指導はどのようにしたのでしょうか。
A(監督):2番目の質問からお答えします。アマンダ役を探すために、多くの子役の方に会いました。ただ、多くの演技経験のある子供たちに会って、気になることがありました。それは、サーカスの猿のように、親や周りに望まれたように演じる面が気になってしまったこと。そのため、演技経験のある子役から探すのではなく、素人の子供からアマンダ役を探すことにしました。ビラを作り、学校や体操教室などいろんなところでビラを配りました。その中で、体操教室に通っていたイゾールさんがチラシを持って現れてくれました。彼女は、赤ん坊のような無垢な面、子供らしい表情を持ちながら、大人のような自分の心を言葉に出来る力を持っていました。また、スカウトした新人ですが、女優として、役者としての心構えを持って、撮影に来ていると感じていました。法律の関係で、撮影は1日に3、4時間しか出来ないという制限がありながら、他の部分は大人の俳優と同じでした。また、撮影環境を、ヴァンサン君や他の共演者も一緒に作りながら、撮影に取り組みました。ラストのウィンブルドンセンターコートのシーンは、この作品の最後に撮影したので、物語としてではなく、彼女にとってのこの作品の撮影のラストということで、気持ちを重ねているようにも感じました。ダヴィッドの取り戻す部分は、意図したところではありませんが、アマンダと生きていくこと、レナと関わり合うことで、暗い状況もあるけれども、「光」があったのだと考えています。
Q(矢田部):ヴァンサン・ラコストさんは、子役のイゾールさんとどのように交流されていたのでしょうか。
A(ヴァンサン・ラコスト):初めは、子役とこのような形で演じるのが初めてということもあり、どれだけ脚本を理解できるか、という点が気になっていました。また、撮影が進むにつれて、彼女の心に(傷が)残ってしまうのではないか、と心配しました。初めての撮影の時は、コミカルな「兄」として交流したら良いのか、父親的に交流したら良いのか、迷っていましたが、物語の前半は、主人公もどのように関わったら良いのか、と悩んでいる部分だったので、そのままで交流するようにしていました。撮影がラストに近づくにつれて、良い関係性になったと思います。撮影の合間は、待ち時間が多いので、一緒にぬいぐるみで遊んだり、パズルをしたりしていましたよ。
Q:物語の節目の悲劇的なシーンや家族の絆を表現するシーンで、公園のピクニックシーンが採用されていましたが、意図的なものでしょうか。
A(監督):まず、テロ事件を扱うということは、被害者の方もいらっしゃるので、不適切な取扱いはしてはいけないと考えていました。よって、テロ事件としては、まったく異なる事件として描きました。公園は身近であると同時に、抽象的でおとぎ話のような部分を持っています。舞台を美術館などに設定するのは、この物語では違うと考えていました。
再生の物語だけでない2重構造
テロ事件で家族を失い、友人たちも被害を受けた主人公と姪を描いていますが、単なる再生の物語ではなく、母親を失った姪の「親」として、主人公の心のあり様が少しずつ変化していく物語。この物語の素晴らしいところは、この主人公ダヴィッドとアマンダとの心の距離感が少しずつ近づく様を繊細に描いているところ。家族を失った悲しみに暮れる中でも、それぞれを思いやり、感じながら進んでいく姿を、絶妙なタッチで描いている。「光」の物語
監督もQ&Aで、たびたび「光」という言葉を使っているが、主人公のヴァンサン・ラコストのキャスティングも、撮影における演出も、「光」を特に意識されている。テロ事件を題材にすると、つい暗さに目に行ってしまうところですが、そうではなく、その先の「光」を表現したいという監督の意図がよく伝わる作品になっている。子役の使い方
昨年、カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝監督も子役に対する演出が注目されましたが、この作品でも鍵となるのが、アマンダという子役ということで、監督もキャスティングから苦労されていたようだ。演技経験のある子役がダメということではないが、まだ、感情表現がストレートになりがちの子供たちをどう演出するのか、が作品の成否を左右することも多い。今回のアマンダ役のイゾールちゃんに出会うことが出来た監督はとても幸運であっただろうし、作品としても、好きな奇跡であった。作品全体として
母親を失った子供だけを描きがちなテーマの中で、主人公や怪我をした友人、知人、事件を後から知った人など周辺部分に気を配って演出されているのは、昨年の『ワンダー 君は太陽』と共通点のある部分で、この作品の素晴らしさのひとつである。この作品を観ることで、自分も少しだけ成長した気持ちになれる、そんな素敵な作品です。おススメ。『アマンダと僕』公式サイト
http://www.bitters.co.jp/amanda/
『アマンダと僕』Amanda IMDB
https://www.imdb.com/title/tt7491144/







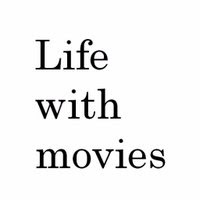
0 件のコメント:
コメントを投稿