 |
| (C) Black Ticket Films |
 |
| (C) Black Ticket Films |
カースト制度にも入らない最底辺ダリト(不可触民)で、社会からも、家庭内からですら、差別的な扱いを受ける女性たちが運営する独立系メディア「カバル・ラハリア」が世界的に注目を集めている
 |
| (C) Black Ticket Films |
「カバル・ラハリヤ」は“ニュースの波”という意味で、2002年にウッタル・プラデーシュ州チトラクート地区にて、ダリトの女性たちによって週刊の地方新聞として創刊される。農村ジャーナリズムとフェミニストを掲げ、地域社会での差別、女性への暴力や性犯罪、ライフラインの不整備、違法労働の癒着と不正、拡大するヒンドゥー・ナショナリズムなど、地元の生活に立脚した草の根報道を続けている。2016年には、独自のビデオチャンネルを立ち上げ、デジタル配信へと移行する。現在、ウッタル・プラデーシュ州とマディヤ・プラデーシュ州の13地区で、30人の女性記者と地方通信員のネットワークを持ち、複数のデジタル・プラットフォームを通じて毎月500万人にリーチしている。「カバル・ラハリヤ」公式サイトにはこう記されている、「あなたのニュース、あなたの声で」(公式ホームページより転載)
カースト、ジェンダー、そして、ジャーナリズム、この作品の提示するテーマは、日本にも、世界にも繋っている
この作品の主人公は、カーストの枠のさらに下とされるダリト(不可触民)に属し、また、宗教的、社会的に女性差別、女性への抑圧が残るインド社会の女性記者たちです。彼女たちは、独立メディアの記者として、汚職、女性への性的暴行、ダリトへの暴力などへ、カメラを、スマホを向け、地方政府、警察、政治家を批判していきます。その活動には、多くのリスクを伴い、また、理解者であるはずの家族の男性からも冷めた視線を向けられます。
しかし、彼女たちが伝える事実は、社会への変化をもたらし、注目を集めていきます。
翻って、私たち、日本のジャーナリズムの状況はどうか。おりしも、ジャニー喜多川氏による性加害問題を、日本の報道機関が報道しなかったことが、性加害問題を広げる結果となったことが、社会問題となっています。
映画メディアも同様です。2022年3月、映画の配給をめぐり、配給会社に圧力をかけた疑いがあるとして、映画会社「東宝」の子会社で、全国で映画館を展開する「TOHOシネマズ」(東京)が、公正取引委員会から独占禁止法違反(私的独占など)の疑いで調査を受けていることが、一部報道機関のみで報道されたが、それ以降の追跡取材は、ほとんどなされていない。
日本のジャーナリズムは、失われてしまったのか。民主主義は、何処へ行ってしまったのか。この作品で映された社会は、インド社会ですが、その内容は、日本社会のジャーナリズムの問題へ直結している。
週刊新聞「Khabar Lahariya カバル・ラハリヤ」
https://khabarlahariya.org/
 |
| (C) Black Ticket Films |
この作品は、「火」であり、「希望」である。
2023年9月12日、大阪・第七藝術劇場において、リントゥ・トーマス監督、スシュミト・ゴーシュ監督によるトークイベントが開催されました。その中で行われたQ&Aより、一部を抜粋してご紹介します。※Q&Aには、作品の内容に踏み込んだものが含まれていますので、ご注意ください。
 |
| 会場の様子 写真提供:第七藝術劇場 |
Q:「カバル・ラハリア」との出会いと映画化のきっかけは?
2009年から、主に女性に焦点をあて、農村で働く方、気候変動の影響を受けている女性の映画を撮っていましたので、フェイスブックで「カバル・ラハリア」に関するフォトストーリーをみた時は、当然、関心を持ちました。この作品の前半に描かれるミーラ(当時:副局長)が、チームへデジタル化の必要性を説明しているシーンがありますが、これが、私たちが初めて彼女たちに会った日のこと。この日から、約4年間、彼女たちと共に映画を創っていったということになります。
Q:映画の撮影や上映にあたり、外部からの抵抗はあったのでしょうか?
私たちは外部からの人間で、外見からもわかるので、できるだけ最小限のチームで撮影しました。私たちに副カメラマンを加え、3、4人で撮影していたし、カメラもコンパクトなものを使用しました。私たちの存在感をできるだけ「小さく」することを心がけました。ただし、撮影においては、目的を隠すことはなく、正直に伝えています。
内容も、彼女たちと相談をして、彼女たちがOKだと言ったものしか撮影していません。彼女たちが取材することを邪魔をしないように、また「こういうストーリーが欲しい」という要望は、していません。
私たちは、この作品を4年かけて撮りましたが、毎年3、4回、10日-15日かけて撮影していたので、周りの人も私たちと顔見知りになってくれました。野菜を売っている人、ホテルの従業員たちも、また来たの?と気軽に接してくれました。結果的に、それが、私たちを守ってくれたと思います。非常にリスクの高い撮影や、緊張する場面もありましたが、無事に撮影することができました。
 |
| スシュミト・ゴーシュ監督(中央) 写真提供:第七藝術劇場 |
Q:映画上映後、マスコミの反応はどうでしたか。ネガティブな反応はありましたか。
反応は、おおむめポジティブなものでした。オスカーにノミネートされたあと、ということもあり、期待が高まっていた。受け止め方として、独立系メディアの重要性ということが言われましたが、皮肉だったのは、それを言っていたのが、保守系のメディアであったということですね。
Q:原題は『Writing with Fire』となっていますが、「Fire」をつけた想いをお聞かせください。
タイトルは2人の意見が合わなくて、なかなか決まらなかった。最終的には、シュミット監督がつけたのだが、私(リントゥ監督)には、最初しっくりと来なかった。ただ、時が経つにつれて、馴染んできました(笑)。作品を製作する中で「火」という言葉が意味を持つようになりました。「火」は、情熱であり、エネルギー。5元素の中で重要で、創造するものであり、破壊するものである。食事を作る「火」であり、燃やしてしまう「火」である。また、「力」を表しています。この映画は、権力について考察するものですが、女性が、男性により、権力から遠ざけられていた、声を取り戻す、力を取り戻す、違う世界を創る、ということをこのタイトルは意味しています。
 |
| リントゥ・トーマス監督 写真提供:第七藝術劇場 |
観客にも、受け入れられたと考えています。歴史的に、映像や文化において、ダリトは被害者として登場することはあったが、この映画は、そのダリト像を反転させています。女性が、知的で活動的であることを映しています。また、ジャーナリズムが危機にさらされている時に、ダリト女性の力強さを表すことができたと考えています。この映画が上映されているインド社会において、カースト、報道の自由について、民主主義社会の価値について、対話するきっかけにこの作品がなっているのであれば、嬉しく思います。市民社会の中で、世界の中で、「対話すること」で、より良い社会が築かれていくと考えている。
Q:今回の作品で、ジャーナリストの社会への役割について、密着されたと思うが、2人はフィルムメーカーとして、社会への役割をどのように考えているか。
私が制作してきた映画は、その時、生きている中で、注目してきたことが反映されています。私たちは「なぜ?」という、好奇心をもって創っている。権力構造がどうなっているのか、その構造から離れた人々は、異なる視点を持っている、ということを取り上げてきました。それにより「希望がみえる」と考えるからです。
国内の状況をみると、フェイクニュースが出回り、希望を失うような時代が続いています。民主主義が弱まっているという状況があります。そんな中でも、彼女たちの活動が、希望をもたせてくれています。国内でも、反カースト運動をしている人々もいるし、独立ジャーナリストとして、このフェイクニュースに対抗しようと活動される人もいる。そういう意味では、希望を持てるのではないか、と想っています。
 |
| 観客の様子を撮影する監督たち 写真提供:第七藝術劇場 |
なぜ変わるのか、というと、一部では「圧力」、そして「善意」があるからだと思います。デジタル化は、ニュースを大きく変えました。以前は、警察に訴えても、答えてくれない、机にいない、ということがあったが、デジタル社会になったことで、この発言をした人(警察)がなにもしなかった、席にいなかった、ということが映像として残っていきます。これがフェイスブックへ掲載され、拡散されていく、これが「公の圧力」となっています。また、彼女たちは、ジャーナリストとして長年活動しているので、さまざまなところに、彼女たちの仲間、同志がいます。警察、地方政府、地方の政治家の中にも、彼女たちを支持し、守っている人たちがいる。作品中でも、女性暴行事件の調査をしている時、窓口の警察官が取材協力するシーンがあるが、あれは、彼女たちの同志がそこにいたということ。静かに活動する中で、協力者、同志が増えています。彼女たちは、最初の報道だけでなく、継続して、その事件をフォローしています。以前は、最低、3回はフォローするということをやっていました。(報道によって)変化(捜査が進展したり、政府が改善工事をするなど)があれば、また、それを報道する。彼女たちが報道すれば、社会が変わるかもしれない、ということが広がっています。
『燃えあがる女性記者たち』
作品情報
監督・脚本:リントゥ・トーマス、スシュミト・ゴーシュ
2021/インド/ドキュメンタリー/ヒンディー語/DCPDCP/93分
公式サイト:https://writingwithfire.jp/
2023年9月16日(土曜)より、ユーロスペース、シネ・リーブル池袋ほかで上映。関西では、第七藝術劇場が、9月30日(土曜)、京都シネマが、10月6日(金曜)、元町映画館が、10月14日(土曜)から順次公開。








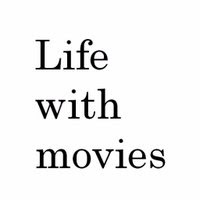
0 件のコメント:
コメントを投稿